バセドウ病と診断されたら知っておきたい治療費と医療保険について
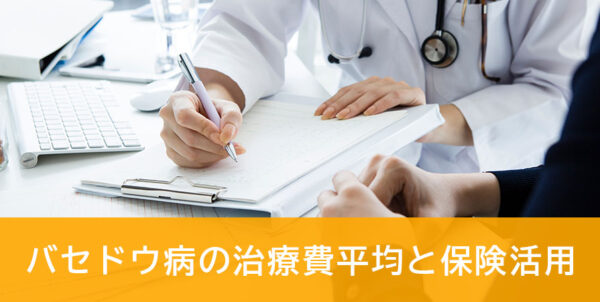
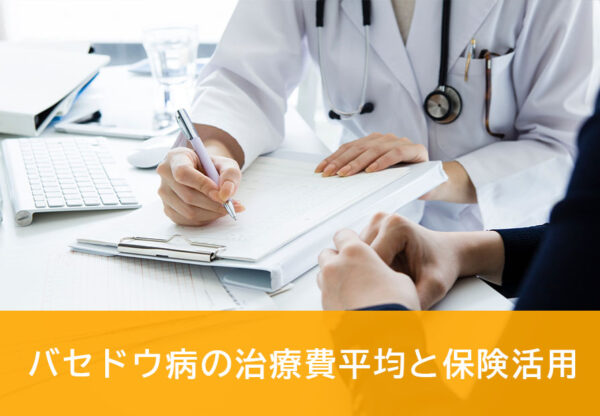
バセドウ病と診断されると、治療費や将来の医療費負担について不安を感じる方も多いでしょう。
しかし、利用できる公的支援制度が複数用意されており、診断後でも加入できる医療保険の選択肢があります。
この記事では、バセドウ病患者が知っておくべき医療費の実態と公的制度の活用法、保険加入時のポイントを解説します。
この記事の目次
バセドウ病の基礎知識と生活上の注意点
バセドウ病は甲状腺機能亢進症の代表的な疾患で、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで様々な症状が現れます。
動悸や頻脈、体重減少、発汗増加、眼球突出などが特徴的です。
日常生活では、激しい運動や過度なストレスを避け、ヨウ素を多く含む食品の摂取制限が必要になる場合があります。
症状が安定すれば通常の生活を送ることができますが、治療には数年かかることも珍しくありません。
バセドウ病の治療には様々な医療費がかかる
バセドウ病の治療費は、選択する治療方法によって大きく異なります。
長期的な医療費負担を把握しておくことで、家計管理や保険選びに役立てましょう。
抗甲状腺薬による通院治療
最も一般的な治療法は、抗甲状腺薬による薬物療法です。
主に使用される薬剤は、チアマゾール(商品名:メルカゾール)またはプロピルチオウラシル(商品名:チウラジール、プロパジール)です。
通院治療にかかる主な費用(3割負担)は以下の通りです。
・初診時:血液検査、尿検査、甲状腺の超音波検査などで5,000〜6,000円程度
・治療開始後2〜3ヶ月:2〜4週間ごとの通院が必要で、1回あたり3,000〜4,000円程度
・症状安定後:2〜3ヶ月に1度の通院で、1回あたり3,000〜4,000円程度
・薬剤費:1日あたり約30円(3錠)、年間約5,000円
月々の医療費は、治療開始時で8,000〜12,000円程度、症状が安定した後は5,000〜8,000円程度です。
年間では6万〜12万円程度の医療費を見込む必要があります。
なお、治療期間は個人差が大きく、一般的には2〜3年かかります。
手術療法
抗甲状腺薬で効果が得られない場合や、重篤な副作用が出た場合などには、甲状腺亜全摘術または全摘術が選択されます。
入院期間は5〜10日程度(手術2日前に入院、術後5日程度で退院)です。手術費用の目安は、3割負担で平均約23万5,000円、範囲は約20万〜42万円程度となっています。
アイソトープ治療
放射性ヨウ素のカプセルを内服することで、甲状腺細胞を破壊する治療法です。
外来治療(連続2日間の通院)または入院治療(約1週間)で行われ、費用は3割負担で平均約6万6,000円と、手術と比較すると費用は安価で、経済的負担が少ない治療法です。
治療効果は緩やかに現れ、約半年かけて本格的な効果が出ます。その間は抗甲状腺薬を再開し、月1回程度の通院が必要です。
多くの場合、治療後に甲状腺機能低下症となるため、生涯にわたって甲状腺ホルモン薬の服用が必要になりますが、この薬剤は安価で副作用もなく、年2回程度の定期検査で済みます。
利用できる公的支援制度
バセドウ病の治療費負担を軽減するため、複数の公的支援制度が用意されています。
制度を正しく理解し活用することで、経済的な不安を大きく軽減できます。
健康保険の高額療養費制度
1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。自己負担限度額は所得区分によって異なります。
年収約370〜770万円の場合は月額80,100円+α(多数回該当の場合は約4万4,000円)、年収約370万円以下の場合は月額約5万7,600円です。
手術や入院時には特に有効で、事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、病院窓口での支払いを限度額までに抑えることができます。
健康保険の傷病手当金
バセドウ病が重症化して仕事を休まざるを得なくなった場合、健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。
連続する3日間の待期期間後、4日目から最長1年6ヶ月間、標準報酬日額の約3分の2が支給されます。
申請には医師の意見書が必要です。勤務先の健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に問い合わせてみましょう。
ただし、傷病手当金は健康保険(被用者保険)の制度であるため、国民健康保険に加入している個人事業主やフリーランスの方は原則として対象外となります。
医療費控除
年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えた場合、確定申告により所得税・住民税の還付が受けられます。
バセドウ病の通院・入院費用が対象となり、家族全員の医療費を合算できるため、領収書はしっかり保管しておきましょう。
障害年金
バセドウ病が重症化し、日常生活や労働に著しい支障がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。
甲状腺疾患での認定は少ないものの、心不全や視力障害などの合併症により認定されるケースがあります。
初診日から1年6ヶ月経過後(障害認定日)に申請が可能です。症状が重い場合は地域の年金事務所や社会保険労務士に相談してみましょう。
バセドウ病患者が加入できる医療保険・生命保険とは
バセドウ病と診断されていても、医療保険やがん保険には加入できますし、治療状況によっては緩和型でない「通常の医療保険」に加入できることもあります。
判断基準となるのは、
・治療開始からの経過期間
・症状の安定度
・手術の有無
・合併症の有無
などです。
特に、抗甲状腺薬で症状が安定し、寛解状態にある場合は、加入できる可能性が高まります。
ただし、甲状腺に関する疾病は一定期間保障対象外とする「部位不担保条件」が付加されることもあります。
この条件は通常1~5年間で、期間終了後は全ての保障が受けられるようになります。
保険会社によって審査基準が異なるため、ご加入を検討の方は保険ウィズまでお気軽にご相談ください。
引受基準緩和型の医療保険も選択肢になる
通常の医療保険への加入が難しい場合の選択肢として、引受基準緩和型医療保険があります。
これは告知項目が3~5項目程度に簡略化された保険商品で、「過去3ヶ月以内に医師から入院・手術をすすめられたか?」「過去2年以内に入院・手術をしたか?」といった質問に該当しなければ、持病があっても加入できます。
加入1年目は保障額が50%に削減されるケースがあったり、保険料は通常の医療保険より割高になります。
それでも、将来の医療費リスクに備えたい場合には有効な選択肢となります。
どのような保障内容を重視すべきか
バセドウ病患者が民間の医療保険に加入する場合は、特有のリスクに対応した保障内容を重視しましょう。
バセドウ病では眼症(眼球突出)や心房細動などの合併症が起こることがあります。
これらの治療にも対応できる総合的な入院・手術保障がある保険を選びましょう。
甲状腺亜全摘術を受ける可能性を考慮し、手術給付金がしっかり設定されている保険が望ましいです。
手術の種類によって給付倍率が異なる場合があるため、甲状腺手術の給付倍率を確認しましょう。
バセドウ病は長期的な通院治療が必要な疾患です。
一般的な医療保険は、入院を伴わない通院のみでは保障されないことが一般的です。
通院のみでも保障される特約があれば、より手厚い保障が得られるでしょう。
また、「入院後、退院の翌日から120日以内の通院」など条件がついていることもあるので、確認が必要です。
まとめ
バセドウ病と診断されても、高額療養費制度や傷病手当金などの公的支援制度を活用することで、医療費負担を大きく軽減できます。
また、診断後でも医療保険への加入は可能であり、治療状況によっては通常の保険に加入できる場合もあります。
既に加入している保険の保障内容を確認するとともに、新たな保険加入を検討する際は自分の状況に合った保障内容を選ぶことが大切です。
保険ウィズではバセドウ病をお持ちの方も加入できる保険を複数ご案内できますので、保険をお探しの方はお気軽にご相談ください。

 バセドウ病の方も加入できる医療保険・生命保険
バセドウ病の方も加入できる医療保険・生命保険
2 件のコメント
今年5月にバセドウ病と診断され薬の影響等の理由から仕事を退職しました。
8月末までの4ヶ月間は傷病手当を頂きましたが、現在は何も収入がなく職安に求職申請をしましたが正直まだ体調が良くなく求職活動にはあまり積極的に動けていません。
この半年で既に医療費の診察代や薬代合わせて20万円を超えていてとても生活が苦しいです。
この先もまだ治療費がかかると思うと憂鬱です。
何か支援等ありましたら具体的に教えていただけると助かります
鈴木 様
コメントくださいましてありがとうございます。
大変なご状況、お察しいたします。
働くのが難しいほどの体調不良ということですと、あとは障害年金への申請しかないと思います。
ご存知かと思いますが、障害年金の認定を得るのもかなり難しいのです。
障害年金の申請を得意とするFPや社労士もいますので、一度相談し申請をされてみるのが良いと思います。
直接的な解決策をご提示できず申し訳ございません。